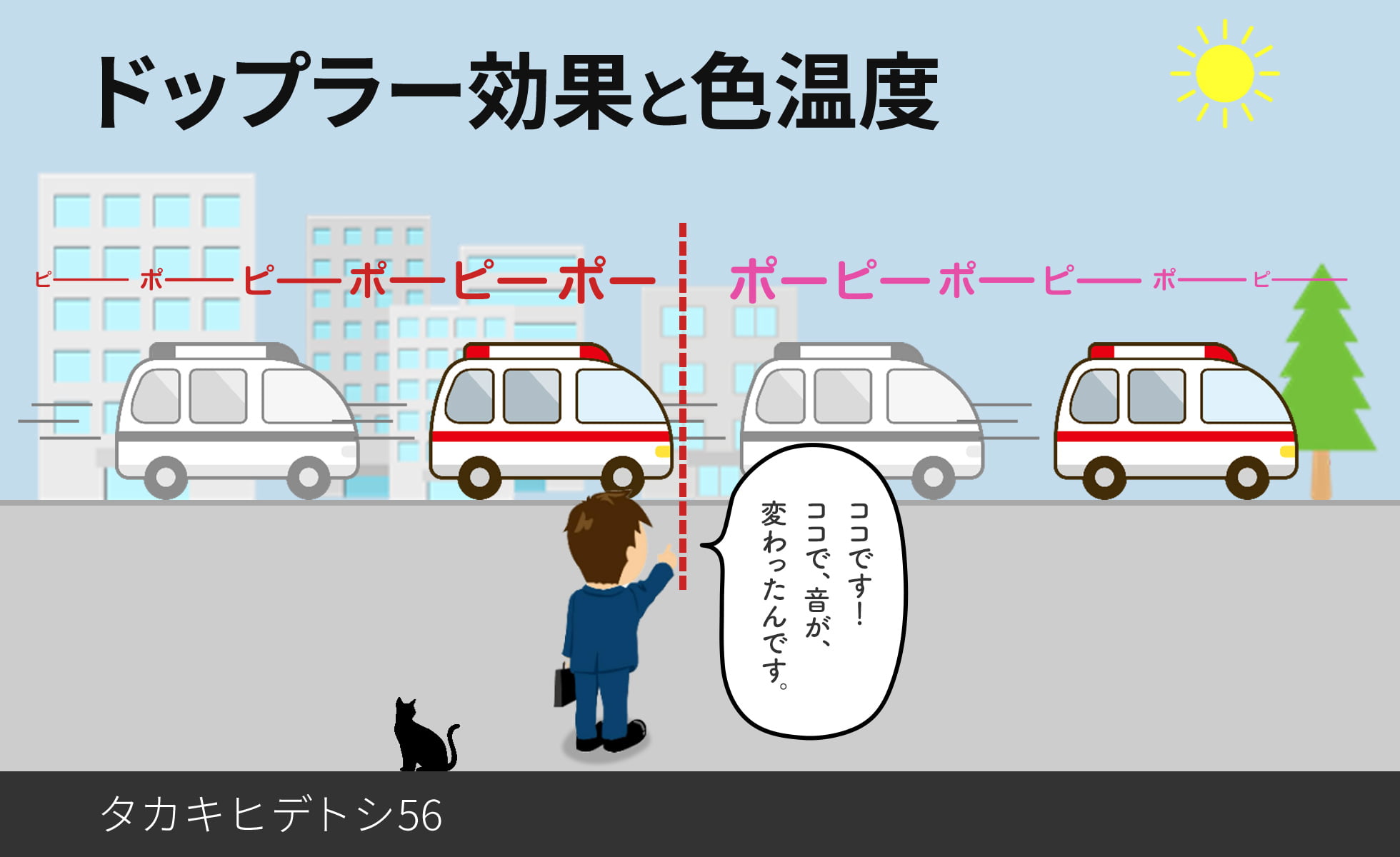43
2024.10
タカキ ヒデトシ56
Interview
- Hidetoshi Takaki
- 住宅デザイン部
ここ数年の住宅照明では【 電球色 】より “ 少し白っぽい光 ” の【 温白色 】が人気のようです。
二つの光色の違いは『 朝日と夕日の空の色の違い 』に似ているので解説してみたいと思います。
《 日の出 / 日の入 》の時刻の定義は「 太陽の上辺が、地平線または水平線に一致する時刻 」
《 日の出 》は、
太陽が地平線( 水平線 )から顔を出し始めた瞬間。
《 日の入 》は、
太陽が地平線( 水平線 )に沈みきって見えなくなった瞬間。
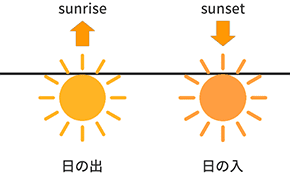
《 日の出 / 日の入 》の時刻の空は、薄暗くはありますが、
屋外で明りが必要なほど、暗い状態ではありません。
この「 日の出前 」や「 日の入後 」の “ 空が薄明るい状態 ” を【 薄明( はくめい )】と呼びます。
『 朝日 』と『 夕日 』は似ていますが、
“ 空の色 ” は、ちょいと違って見えてくる。
『 朝日 』は、少し白っぽく、
『 夕日 』は、少し赤っぽい。
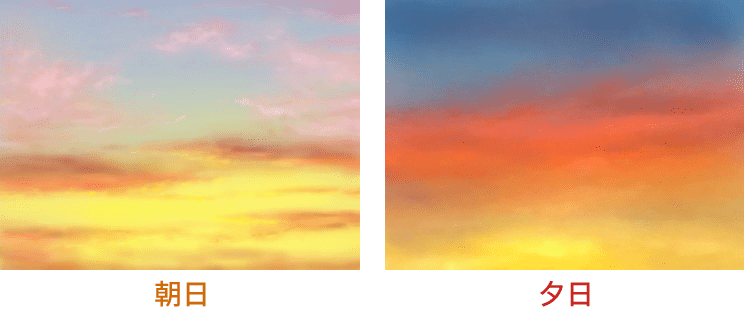
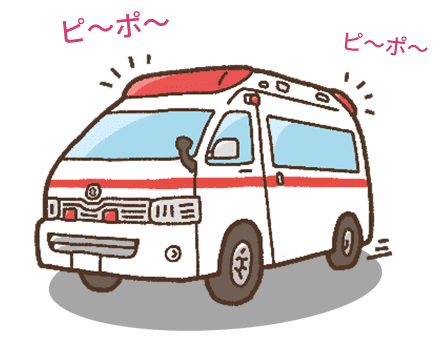
この “ 光の色の違い ” は【ドップラー効果 】によるものです。
【 ドップラー効果 】とは、音波や電磁波などの《 波の発生源 》が移動したり、
その『 観測者 』との間に “ 相対的な速度 ” が存在するときに、波の周波数が、
実際とは異なる値として観測される現象のことをいいます。
いちばん身近で分かりやすいのが【 救急車のサイレン音 】なのですが、
ちょいとその前に “ 予習 ” をしておきます。
私たちの身の回りには、
「 太陽の光 」や「 照明の光 」など、いろいろな光があります。
その光とは《 電磁波 ( でんじは ) 》と呼ばれる、空間を伝わっていく『 波 』の一種です。
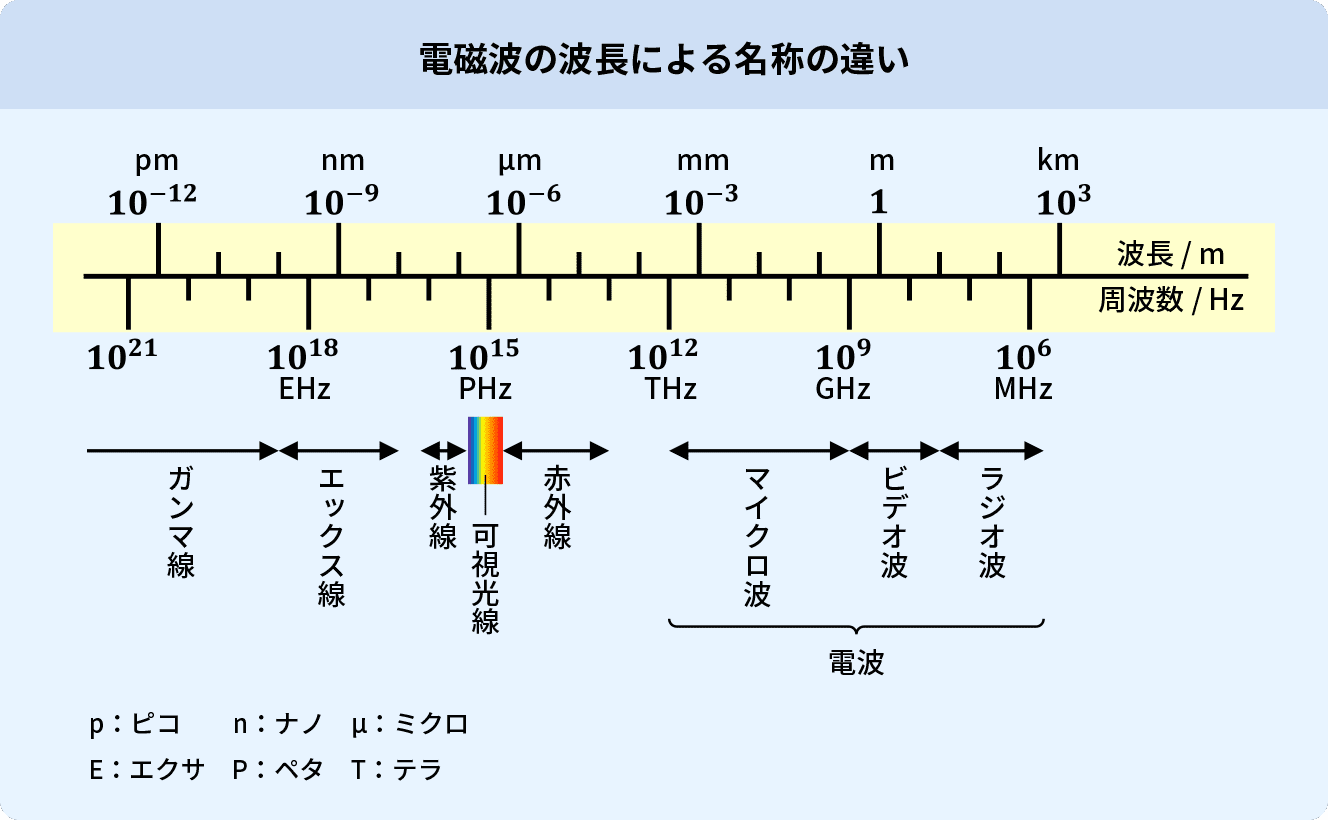
《 電磁波 》 が 1 秒間に振動する回数を『 振動数 』または『 周波数 』と言い、
[ ヘルツ ] という単位で表します。 単位の記号は [ Hz ]
電磁波の性質は “ 振動数の大小 ” によって、ずいぶん変わるので、
振動数の範囲によって、種々の名前が付けられています。
波長とは “ 波の山と山または谷と谷の間の距離 ” のこと。
波の速さ、つまり、
波が 1 秒間に伝わる距離を振動数で割ったものが『 波長 』です。
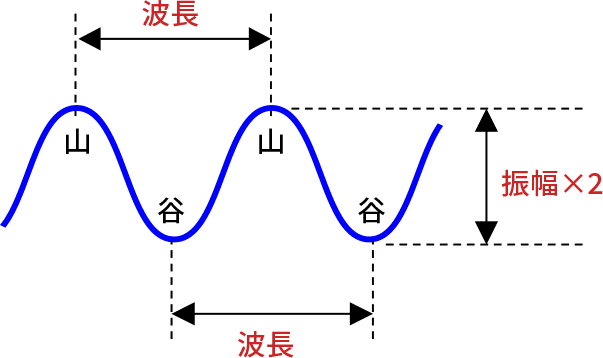
電磁波のうち “ 人間の肉眼に見える ” のは、波長がおよそ、
400 ~ 800 nm( ナノメートル )の範囲で、これが《 可視光線 》といわれる狭義の光。
[ nm( ナノメートル )] というのは、10 億分の 1 m 、つまり 100 万分の 1 mm のこと。
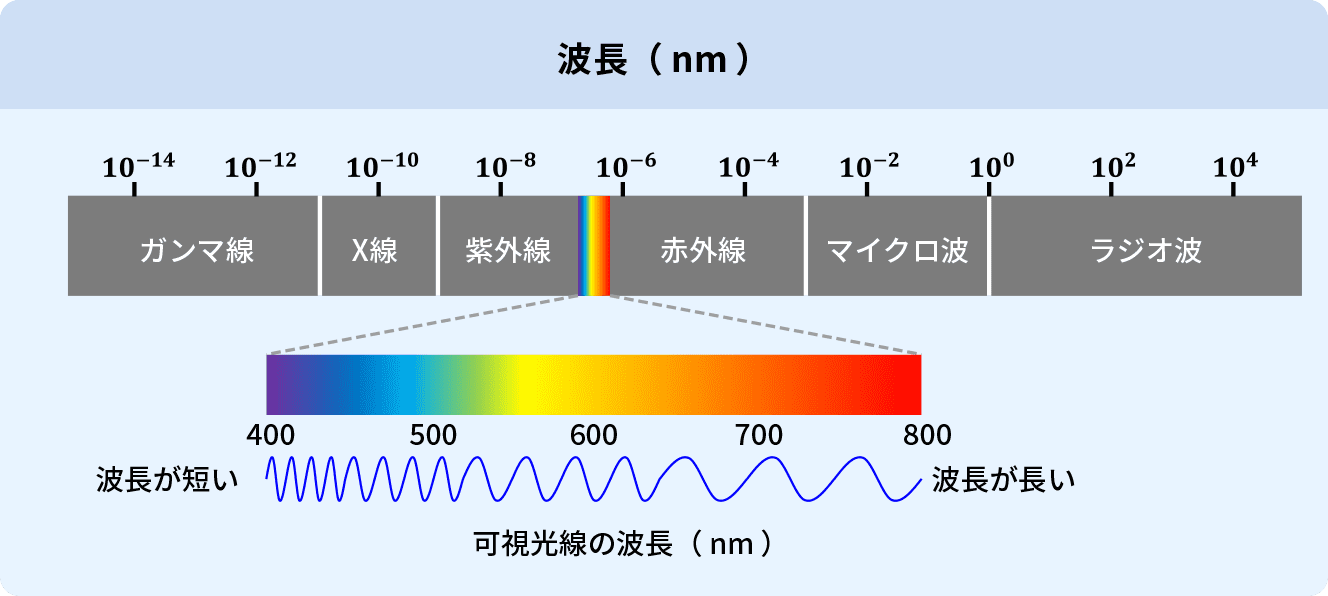
《 可視光線 》 visible light は、人間の目に《 光 》として感じる波長範囲の電磁波で、
波長範囲の下限は、360 ~ 400 ナノメートル ( nm )。
波長範囲の上限は、760 ~ 830 ナノメートル ( nm )。の単位で表されます。
まぁ、光の波長のうち、人間が “ 色 ” を感じられるのは、
『 約 380 ~ 780 ナノメートル( nm )の波長の電磁波だ! 』
と、覚えておくといいでしょう。
『 音 』も《 光 》も、空気中を進む速さが決まっています。
『 音 』は約 340 m / 秒。 《 光 》は約 30 万 km / 秒で進んでいく。
『 音 』の空気中の速さは、気温が約 15 ℃ のときのもので、
この速さを [ マッハ ] という単位であらわして [ マッハ1 ] と言います。
《 光 》の速さは約 30 万 km / 秒。
たった 1 秒で地球を約 7 周半する速さ。
《 光 》の速さをマッハであらわすと、
300,000 ÷ 0.340 = 882352 … なんと [ マッハ 88 万! ]
《 光 》は『 音 』の 88 万倍の速さで伝わることになる。
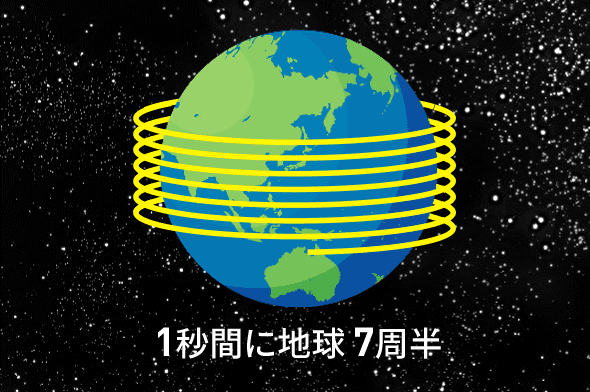
こんな猛スピードの計算なんて、僕にはできないので、
そこで [ 音の速さ ] についての出題をしてみます。
問題
船から海底に向けて『 音 』を出したら、6 秒で返ってきました。
海底の深さは何メートルでしょうか。
ただし、水中を伝わる音の速さは 1,500 m / 秒とします。
船から海底に向けて音を出し、6 秒で返ってきたので、
音が伝わった距離は 1,500 × 6 = 9,000 m
ただし、これは答えではありません。
ここでの音は、海面から海底までを “ 往復 ” しているので、
9,000 ÷ 2 = 4,500 m
答え: 海底まで 4,500 m
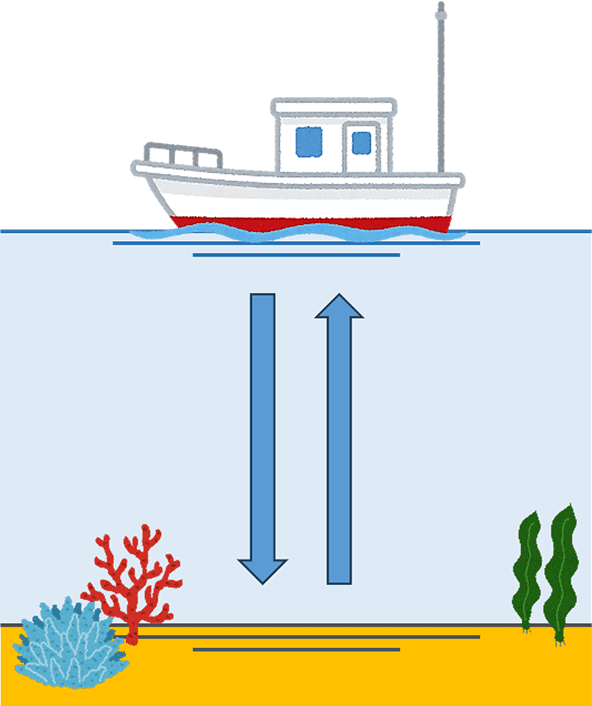
では【 救急車のサイレン音 】でみてみましょう。
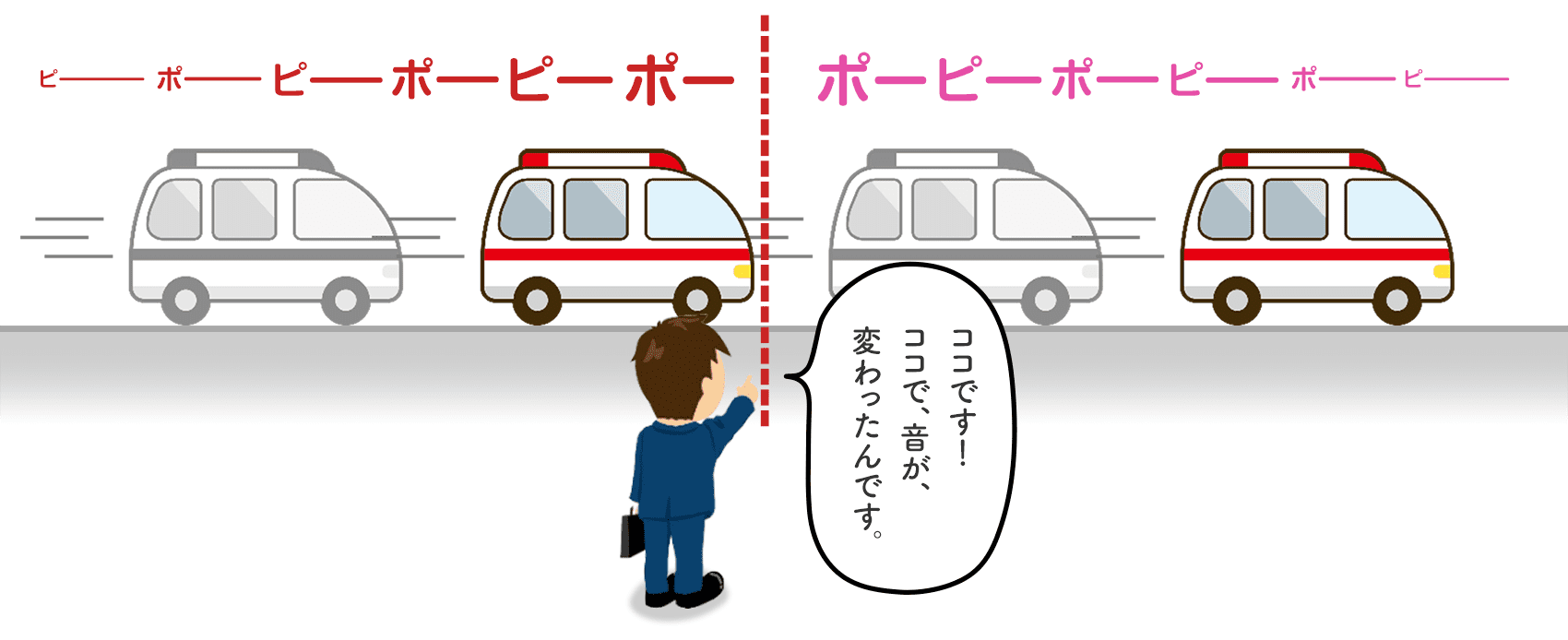
救急車が『 ピーポー ピーポー 』というサイレンを鳴らしながら遠くからやって来るとき、
その音はどんどん大きく、早くなって聞こえてきます。
ところが僕の目の前を通り過ぎると、そのサイレン音は『 ポーピー ポーピー 』に変わって、
その音はどんどん小さく、遅くなって聞こえるようになります。
これが【 ドップラー効果 】と呼ばれるもので、
音が移動しながら音を発するとき、観測者に対して、進行方向に進む音は波長が短くなり、
反対に、進行方向と逆方向に進む音は、波長が長くなるためにおこる現象です。
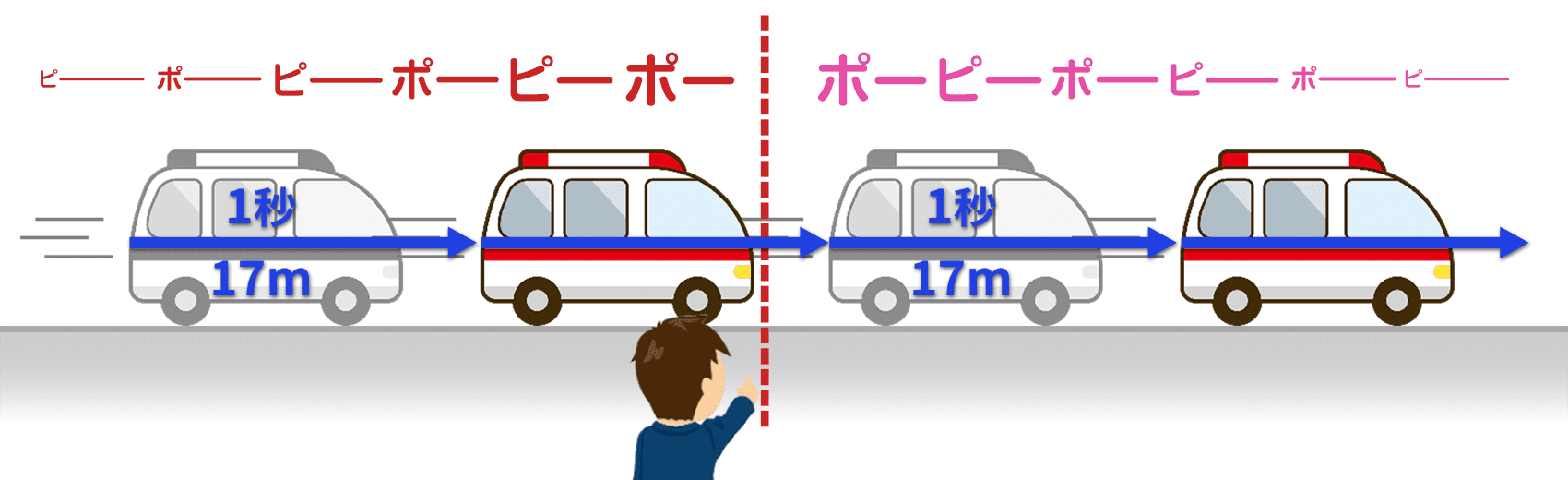
救急車が時速 60 km / h で走っているとします。秒速で考えると、
60,000 m ÷ 3600 秒 = 16.66 … となり、救急車は 1 秒間に約 17 m 進むので、
救急車が近づいてくるときは、同じ方向の音を追いかけることになります。
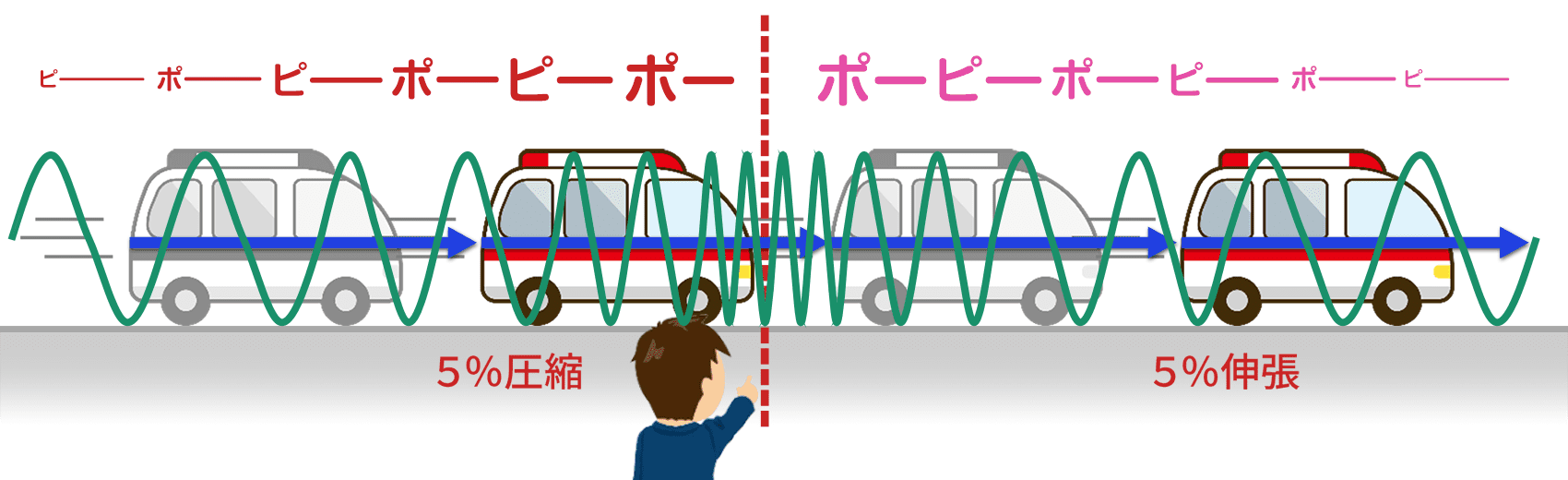
『 音 』は 1 秒間に約 340 m 進むから、17 ÷ 340 = 0.05 なので、
近づいてくるときは、音の波が 5 % が圧縮され、
遠ざかるときは逆に、音の波が 5 % 伸張されることになるので、
周波数に 10 % の違いが生じることになる。
これが『 ピーポー ピーポー 』から『 ポーピー ポーピー 』へ変わる正体。
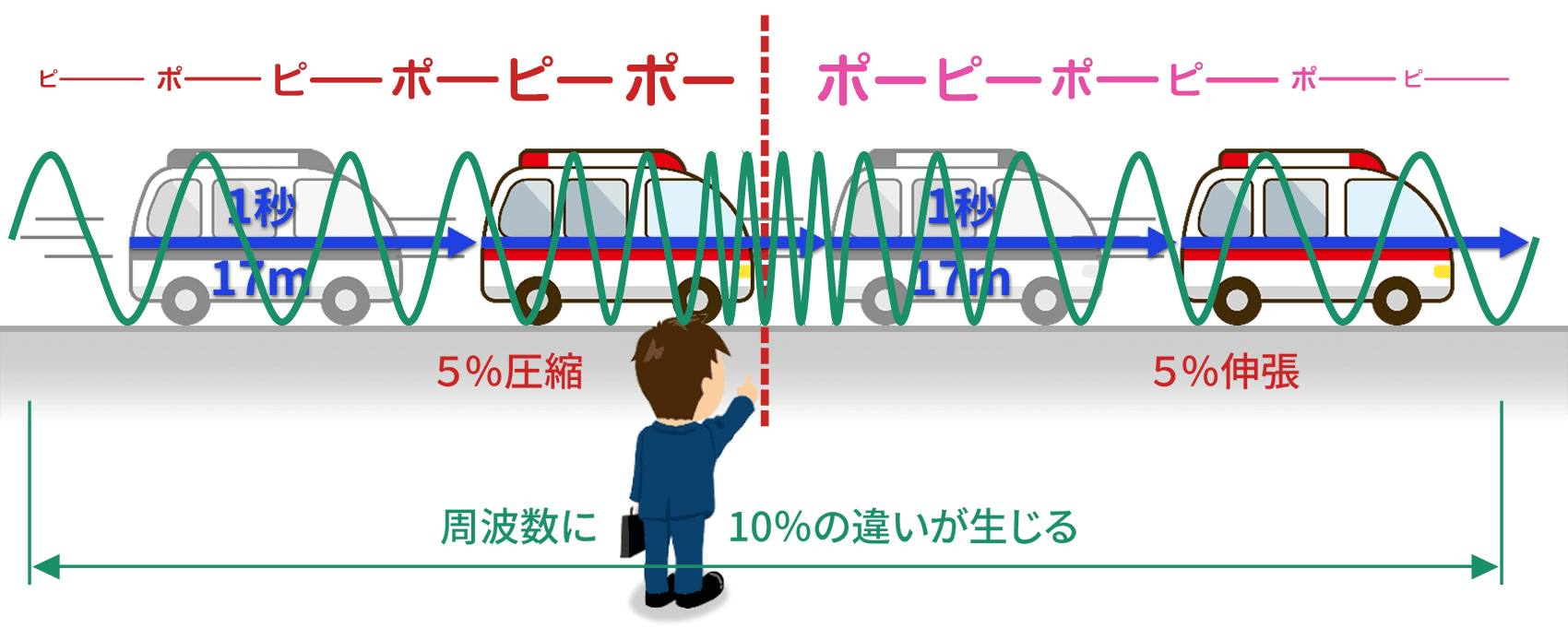
下図のように、地球は回転しています。
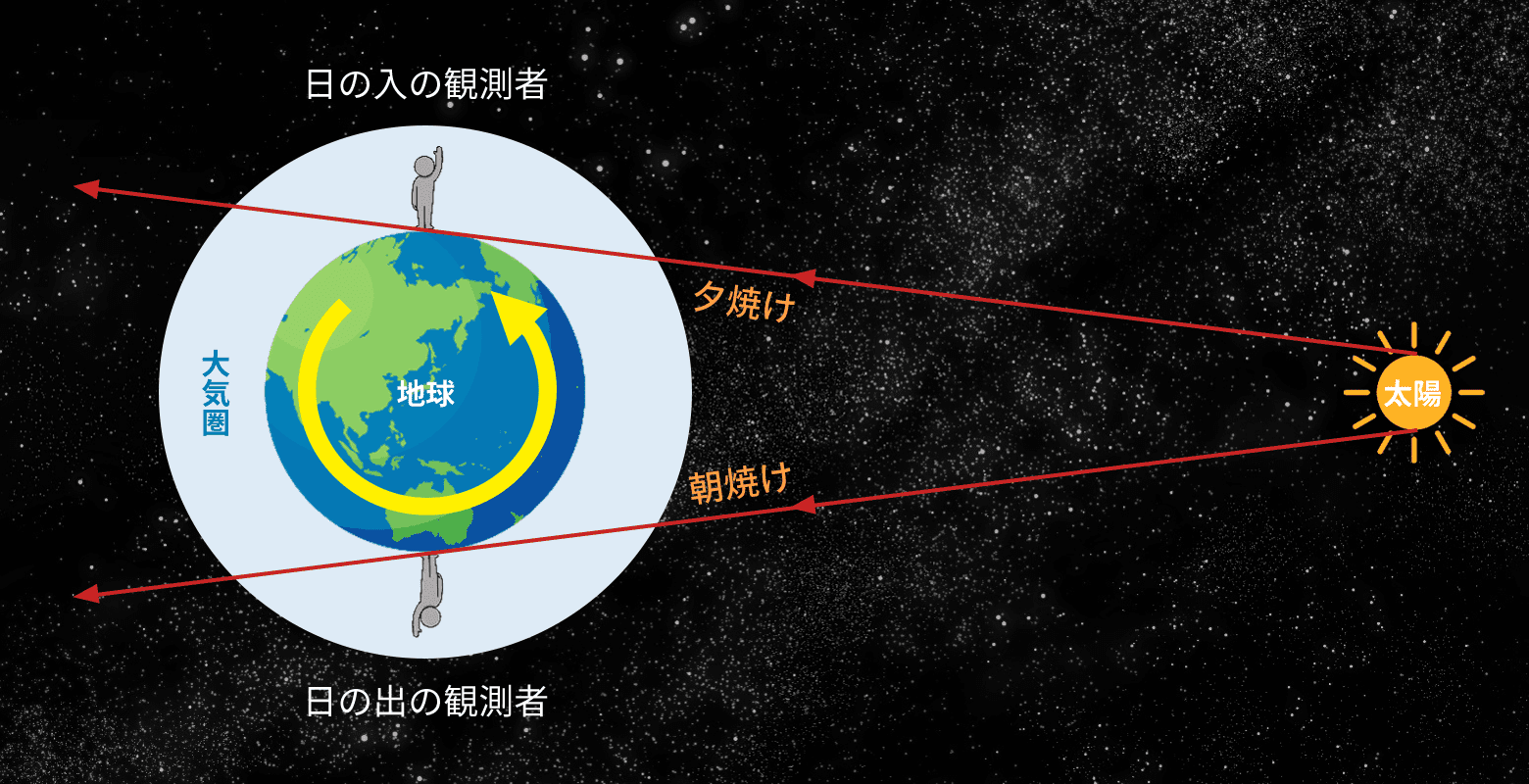
地球と太陽の位置関係で、観測者の太陽に対する相対速度が、
日の出 / 日の入のときが一日で最も大きくなります。
つまり日の出のときは太陽の光が急接近し、日の入のときは太陽の光が急速に遠ざかる。
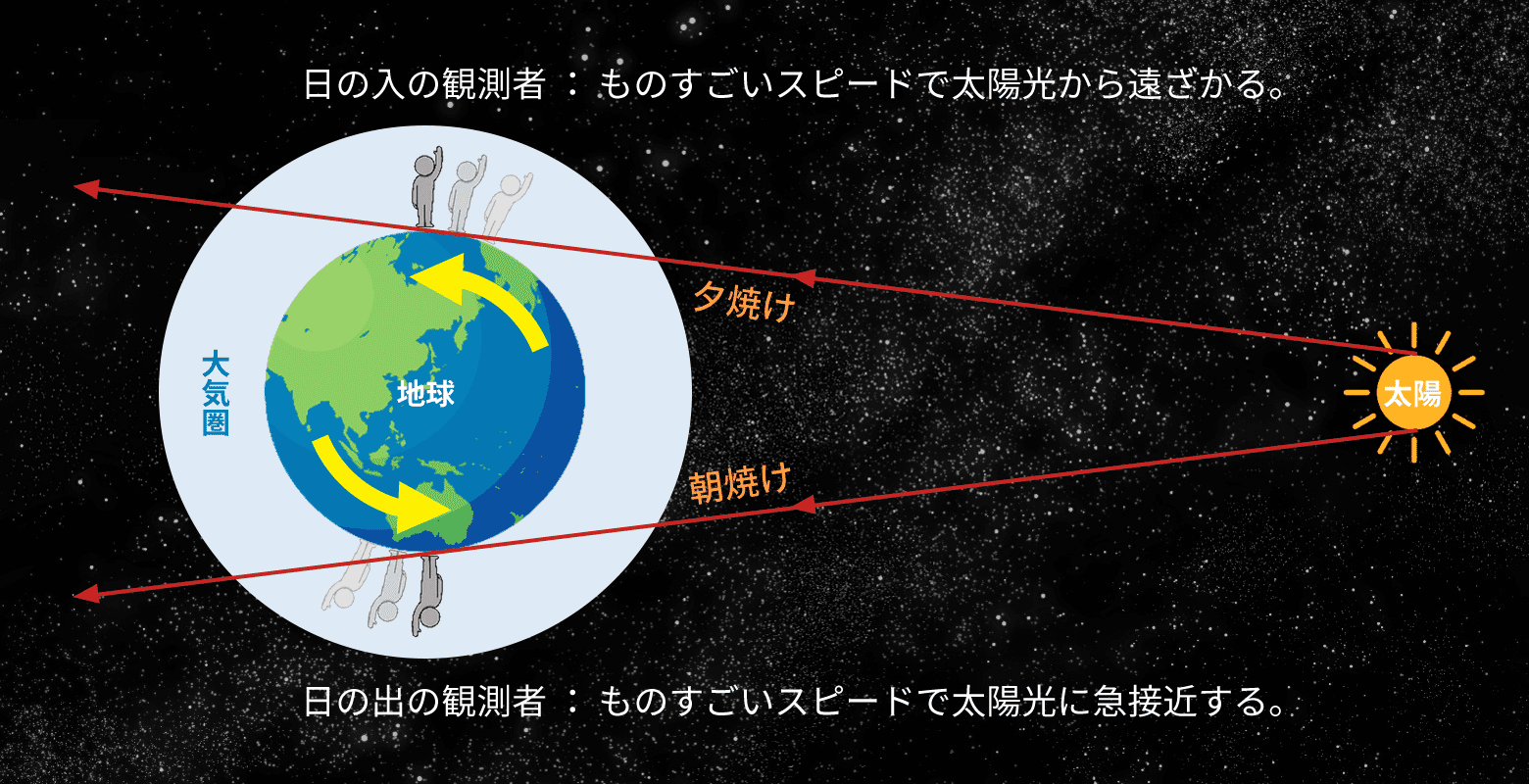
この現象を【 救急車のサイレン音 】に置き換えるとこういうことです。
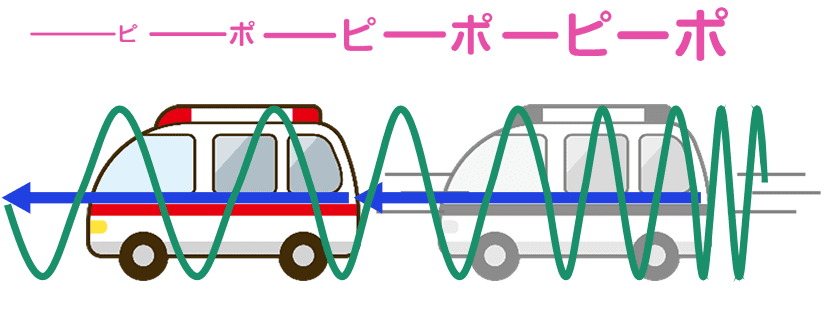
「 光から逃げろ~ !」
約 30 万 km / 秒でやってくる光に対して、
赤道上で 約 460 m / 秒の地球の自転速度で遠ざかる。
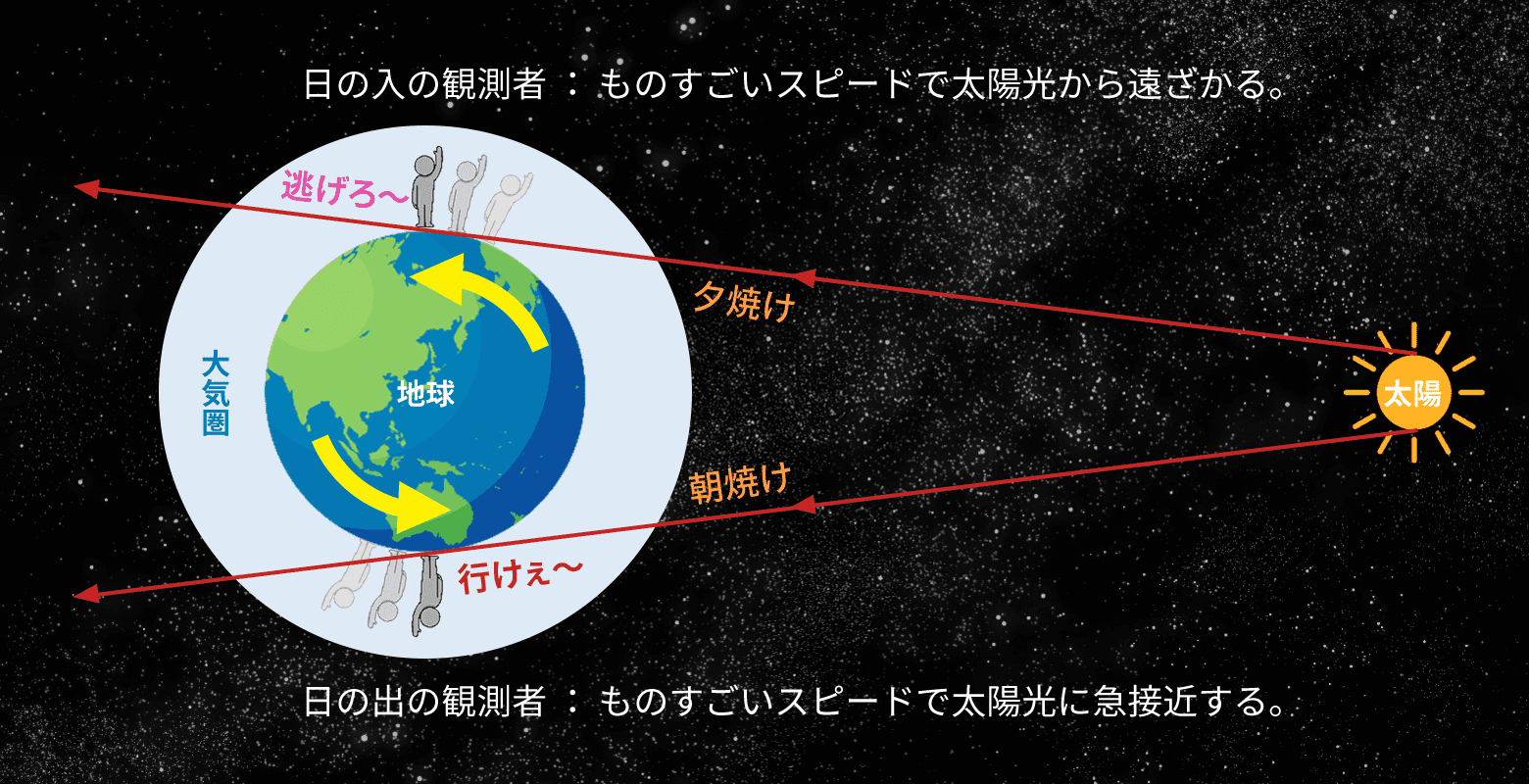
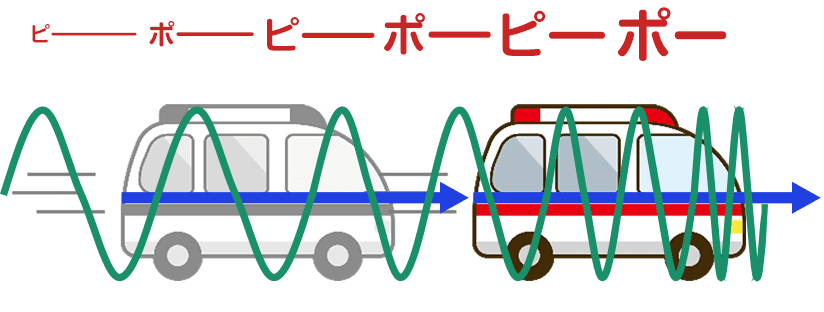
「 光に向かって行けぇ ~ !」
赤道上で 約 460 m / 秒の地球の自転速度で、
約 30 万 km / 秒でやってくる光に対して接近する。
さきほど、人間の目に《 光 》として感じる波長範囲の電磁波が《 可視光線 》で、
光の波長のうち、人間が “ 色 ” を感じられるのは、
『 約 380 ~ 780 ナノメートル( nm )の波長の電磁波だ! 』
と、覚えてもらいましたが【 光の色 】についても同じことが言えるのです。
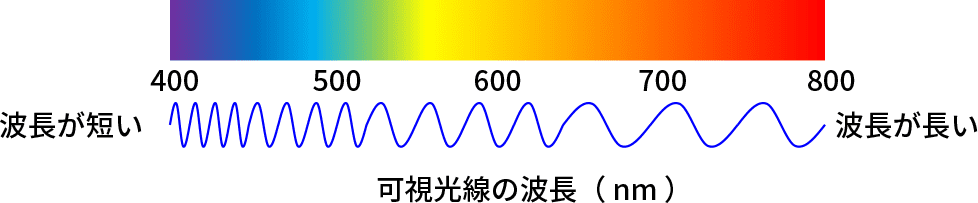
【 ドップラー効果 】は、
光の発生源と観測者が近づいているときは波長が短くなり、
遠ざかっているときには波長が長くなる。
つまり《 光 》は、
観測者が相対的に近づいている『 日の出 』のときは、波長の短い青色が強く見え、
遠ざかるときの『 日の入 』のときは、波長の長い赤色が強く見える。と、いうことです。
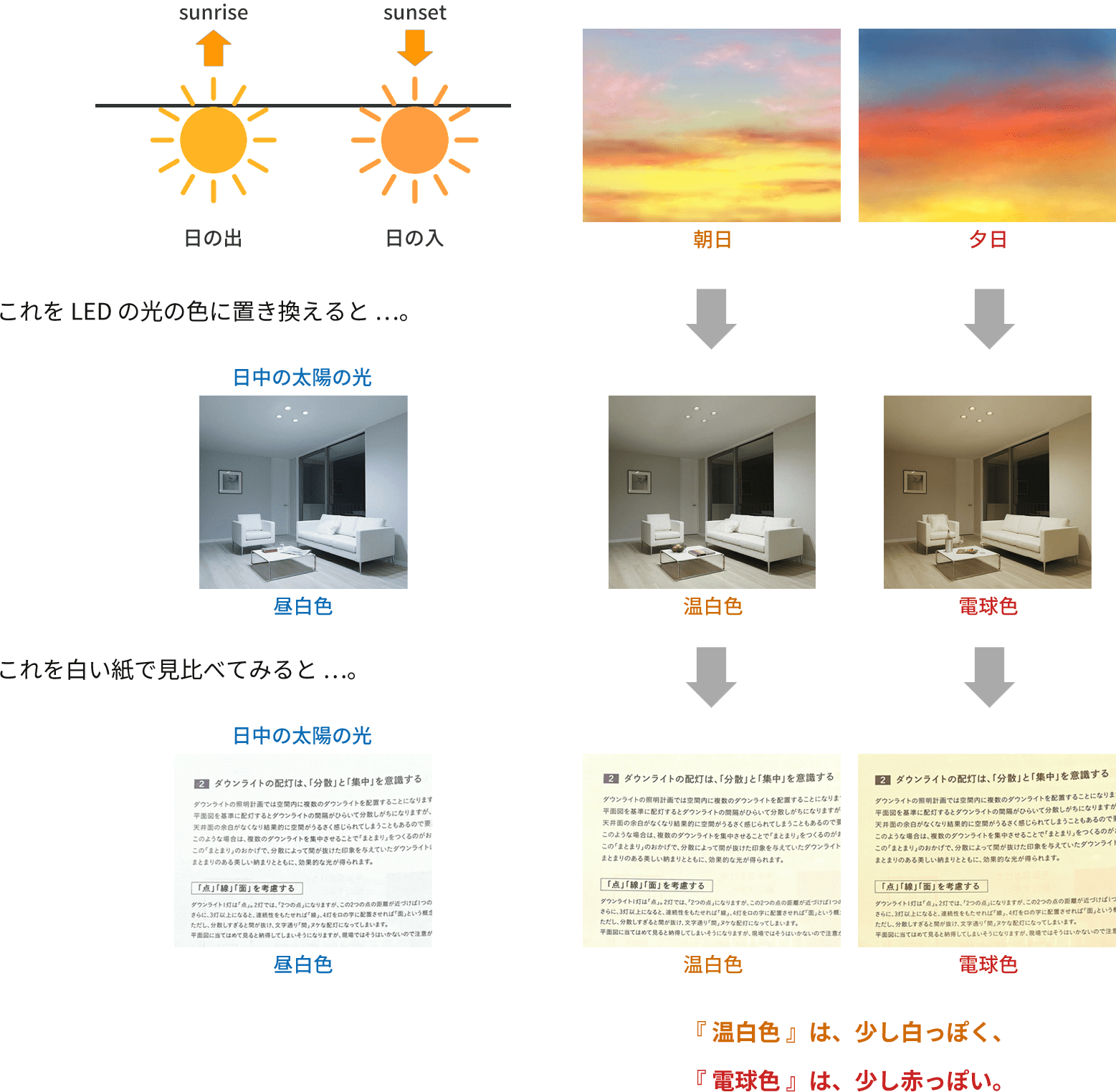
昼間の「 白くて明るい光 」から解放された《 日の入から日の出 》までの夜の空間には、
確かに、赤味を帯びた『 電球色 』が落ち着いた雰囲気を醸しだすことができます。
でもね …。
白い紙で見比べたように “ 白い紙が赤味を帯びて見えてくる ” のが『 電球色 』の光 。
白と黒の対比によって文字が見やすい『 昼白色 』と比べると、読みづらくなります。
この読みづらさが “ 暗い ” と感じさせてしまう一つの原因。
だから …。
「 電球色は雰囲気がいいのは分かるんだけど明るさがちょっとねぇ 」って方には、
これから “ 活動的な朝 ” を迎えようとする、少し白っぽい光の『 温白色 』がお勧めです。